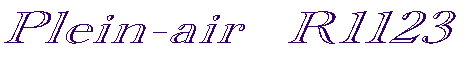
ボディ左側面・8
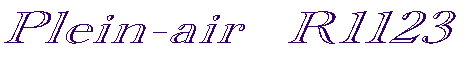
![]()
ボディ左側面・8
 |
何をしているかというと、屋根が無い分重みでお尻が下がるので延長のフレームを出しジャッキボルトで補強をしているところです。 |
| まだ手付かずの荷台フロア裏側。 |  |
 |
酷く錆びている部分はありませんが、「錆びてるじゃん」。って突っこまれそうですが、可愛い方 |
| 全体に薄っすらと新車時の防錆塗料は残っています。 |  |
 |
寝板に仰向けになり、カップブラシを付けたディスクサンダーを片手で持ちひたすら錆を落とします。 |
| 表に浮いた錆はすべて落としました。 |  |
 |
地肌まで出すと面倒なので、これぐらいにしておきます。 |
| 荷台フロアーもゴムマットで隠れてしまうのでほどほどに。 |  |
 |
シンナーで埃取り、脱指の為全体に拭きます。 |
| 脱指後スプレーガンでPOR15を塗ります。 |  |
 |
荒隠し終了。 |
 |
|
 |
もう一コート、チッピングコートを塗ります、新車はしてありません。正直、防錆と荒隠しのために塗りました。 |
 |
|
 |
フェンダーの継ぎ目にもしっかりと、 |
| 後は全てボディ同色に塗装します。 |  |
 |
次は幌屋さんに持ち込むのに幌枠を付けています。 |
| こんな感じでボディ側面・リヤハッチのラインに沿わせて取り付きます。 |  |
 |
ここで大誤算が!幌枠はこのタイミングまでほぼノーチェック、そんなに痛んでいないと思っていた枠も、よく見ると中途半端に繋いであるし。幌を慎重するのにちょっとつりあわないので急遽作り直すことに、と言ってもやり方は何も考えていない、ノープラン。 |
| 幌枠は2本で構成されていて元々のものは同じ形状のものを2段重ねになっている。でも繋いであるところを直そうとしたとき手の付けられない状況に陥いる。 |  |
 |
幌の内側になるし、コーナーだけこれでなんとかならないかとためしにやってみたものの、強度不足で使い物にはならない。 |
| それで作戦変更、16mmステンレスの丸パイプは硬すぎて曲げるとシワが入り使い物にはならないので、鉄で外径16mm・肉厚1.6mmの丸パイプをネットで購入、何で曲げるかというと、少し用途は違うが電気工事用のパイプベンダー、勿論ハンドパワーで曲げます。 |  |
 |
左右対称として、中心からの曲げ始めの距離・角度・曲げRと寸法さえ解ればそんなに難しい作業ではありません、パイプの下にあるのがベンダーテコの原理を利用して曲げます、コーナーRは確かR130だったはずです。流石に一回で90度曲げるのは無理があるので、一回30度ぐらいで3回ぐらいに分け曲げます、R130から円周を求め、12で割り30度の円周を求めその距離間で30度を曲げるといった地道な作業です。 |
| ベニア板にラインをケガキそれに合わせ曲げます、 |  |
 |
新設の幌枠は2段重ねでは無く、幌をたたんだ時に内側に入るよう、パイプ径だけ幅の狭い枠を作成します。 |
| なんとか格好はつきました、 |  |
 |
幌枠の角度、位置を決めます。 |
| 少し解りにくいですが、ウインドウ枠の上に付くパーツにベルトが付き全体の長さを決めています。枠は幌の形を決め、開閉時のガイドになります。 |  |
 |
枠とベルトはビスで位置を固定、側面に貼ってある紙はカタログの側面写真でそれを見ながら、「これぐらいかな?」と少しずつ位置を変え確認を繰り返します。枠の角度が変われば幌のラインも変わるので一発勝負です。 |
| 大体形は決まりました、このままこれに合わせて幌を作ってもらうので後から変更は効きません。 |  |
 |
梁にぶら下げシルバーメタリックに塗装をします。 |
| 幌作成のために、積載車で運びます、久しぶりにガレージから外に出ました。 |  |
 |
やっとここまできたな、と幌ちゃんとできるかな?の気持ちが。 |
| 同じ県内の、河嵜・奥村両氏の協力を得て積載車に積み込みます。 |  |
 |
2016年12月末 |